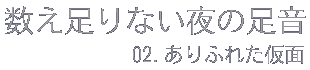
は夢を見ていた。
意識が揺らぐような、それでいて居心地の悪い夢。
そこは緑が生い茂り、ところどころに木が生え、奥には広大な湖があるというのに、動物の一匹も見当たらない。
いる者といえば、湖の少し手前で何やら話をしている少年と少女が2人。
少女の顔はよく見えないが、少年の顔ならの位置からよく見えた。
その顔には、吐き気がするほど見覚えがあるはずなのに、何故だか思い出すことが出来ない。
2人の元へ駆け寄り「君は誰?」と問いたいが、の体は自由を失っている。
自分の夢の中だというのに、まるで、誰かにコントロールされているかのようだった。
頭がぼんやりとする感覚に囚われながら、悪夢にも似たその夢の景色は徐々に揺らぎ始める。
次に意識を取り戻した時、目に映ったのは見慣れた寝室の天井だった。
襲い掛かるような倦怠感は先程の夢の所為だろうとは溜め息をつく。
「朝から溜め息だなんて、幸先が悪い。イヤになっちゃう。」
眠気は残っているが、あの夢に戻ることは避けたい。
そう思いながら、ゆっくりとベッドから離れれば、それこそ夢にしてやりたいと強く願うほど憎らしい声が耳を刺激した。
「ノロノロしている暇があったら支度をするべきですね。時計を見てご覧なさい。」
断りもなく寝室に入られたことへ苛立ちながらも指差された方向へ嫌々顔を向ける。
時計の針が示した時刻は、8時20分。
普段なら朝食を済ましている時間だ。
「どうして起こしてくれなかったの!?」
「何度も声を掛けましたよ。やれやれ、自身の目覚めの悪さを悔やむより、他人にその責を押し付けるとは、呆れてものも言えませんね。」
「十分にお話できているからご安心を。それより出かける準備をしてちょうだい。」
「お言葉ですがさん、こちらは既に終えていますよ。あとは貴女を待つのみです。」
「き、着替えるから、出て行って!」
「これは失礼しました。時間がありませんので、お急ぎ下さいお嬢様。」
わざとらしい程丁寧にお辞儀をした骸にクッションを投げつけたい気持ちを抑えて、は身支度を始める。
天気や気分に応じて服やアクセサリーを選ぶのが日課であったが、そうも言っていられない。
とにかく時間がないのだ。
おまけに、これ以上手間取れば、嫌味な執事がこれ見よがしにその隙をついてくるに違いない。
目に付いたワンピースを引っ張り着替えると、普段では考えられない程の手際で化粧をする。
最後に鏡で全身をチェックすると、勢いよく部屋を飛び出した。
「おやおや、これは驚きました。僕の予想では、あと3分はかかると踏んでいたのですが。意外ですよ。」
言い返してやりたかったが納得できる文句が思いつかずには黙秘を決め込んだ。
その様子を眺めながら満足気に微笑む骸は、全てを見透かしているようだった。
「さて、そろそろ出ましょうか。朝食は車内で召し上がりますよね。手配済みです。さあ、お車へ。」
悔しいが、認めたくはないが、骸の仕事は完璧だ。
もちろんに対する自重しない嫌味の数々は無礼に当たるものだろうが、それを差し引いても完璧だった。
が次に言うであろう命令を先回りして準備している。
まるで、心の中を読んでいるかのような正確さで。
たった半日で、の性格をいとも簡単に計ってしまっていて、そればかりではなく、の父からの信頼は強固たるものだった。
その真相を、もちろんが知る由もない。
令嬢の執事という役目を円滑に果たすため骸にはありとあらゆる資料が渡されていることなど。
「大学生活はいかがですか?勉学には苦戦しているようにお見受けしますが、人間関係が良好であれば合格としてあげましょうか。」
骸の運転する車に乗り込み、が朝食をとり始めたところへ早速、嫌味を交えた調査が始まる。
調査と言っても、今回の任務の核に迫るものではない。
言ってみれば、の人間性や交友関係の本心を探るための他愛のない質問だ。
「友人は多いけど、その中でも特に仲が良いのはパオラかしら。ご両親が大学の教授をしていてね、とても勉強のできる子よ。テスト前には頼ってばかり。恥ずかしいけど。」
「なるほど。それでさんもどうにか進級できているわけですね。納得できました。良き友人をもっているようで一安心です。」
「六道さん、あなたね、まるで私を頭の悪い人間のように言うけれど、失礼が過ぎない?」
「気分を害したのなら、否、事実と異なるようでしたら謝罪しましょう。」
前者で止めておけばよかったものを、わざわざ言い直すのだから、尚更腹立たしい。
残りのフレンチトーストを飲み込みながら、はキッと骸を睨みつける。
しかしその威嚇は軽々とあしらわれてしまい、骸の視線はフロントガラスの向こうへと戻された。
ここでが強く出られないのは、自身も非を認めているからに違いなかった。
幼くして母が他界し母の故郷であるイタリアへと渡ってから、言葉も文化も違う異国での生活に戸惑うを可愛がってくれたのは祖母で、彼女があらゆる本を読み聞かせてくれたため、の知識は次々と広がっていった。
しかしその祖母もが10歳になった頃に他界してしまってからは専属の執事と家庭教師が傍を離れない毎日が始まる。
それからは、あれほど好きだった本も毛嫌いするようになり、勉強の時間になると部屋を飛び出し屋敷中を逃げ回っていた。
おかげで大学生になった今でも、学ぶ意欲は人並みを遥かに下回る。
「私が悪いわけじゃないのに。」
思わず、そう呟いてしまったことをは後悔したが、幸い骸の耳には届かなかったらしい。
聞こえぬ振りをしてくれたのかもしれないが、は聞こえなかったのだと思うことにした。
彼の気遣いなど、優しさなど、あるわけないと思い込んでいることもあり、また、そんな一面を見てしまっては今後の防衛策に傷がつくと考えたからでもあった。
「間もなく到着です。僕を睨むのは勝手ですが、その顔でご友人に会うのは控えたほうがよいでしょうね。」
「ほっといて!」
−−−なんて憎たらしい!一瞬でもあの人に紳士を垣間見た私が馬鹿ね。
込み上げる怒りをどうにか落ち着かせようとは深呼吸をする。
それから間もなくして車が止まり、後部座席のドアが開き、車を降りると同時に、向かってくる友人パオラの姿が見えた。
骸に対する怒りは車内に置き捨てて、友人に向けて笑顔で手を振る。
「おはよう、パオラ。そのブラウス素敵ね。よく似合ってる。」
「ありがとう。ところで、そちらはどなた?」
「昨日から来ている新しい執事の六道さん。あまり関わらない方がいいわよ。きっと気分を害すわ。」
「お嬢様も人が悪い。今朝のことを根に持たれているなら謝ります。どうか機嫌を直してください。」
やはり、つい先程までの男とは別人だ。
まるで従順な飼い犬のように困った顔をして、を嗜める。
「ロクドー?変わったお名前ね。でもとってもハンサム。私はパオラ、の友人よ。どうぞよろしく。」
「ええ、こちらこそ。」
敏腕の営業マンも退散してしまうほど爽やかな笑顔を振りまき、手を差し出す。
その仕草にパオラは「まあ」と感嘆の声を上げながら握手を交わすが、彼女の頬がほのかに色付いているのをは見逃さなかった。
−−−私の前とは大違い。いつかその仮面引っ剥がしてやるわ!
「行くわよパオラ、1限の授業に遅れちゃう!」
「待って!それではロクドーさん、ごきげんよう。」
「いってらっしゃいませ。」
本当は顔など見たくもなかったが、どんな様子でいるのか監視をするつもりで振り返ると、門の手前で恭しくお辞儀をしている。
どこまでも芝居がかった男だと呆れて視線を戻そうとした瞬間、あの、人を見下したような目でを見つめ笑ったのだ。
距離が開いてしまったこともあり声までは聞こえぬが、きっとクフフと笑っているに違いない。
そう確信すると怒りのボルテージは更に高まり、校舎へと進む足音が徐々に大きくなる。
背後の男に呪いでもかけてやりたい気持ちをどうにか抑えながら、今日の1限、現代文学の講義が行なわれる教室へと向かった。
「さて、今日は4限目まででしたね。お迎えの時間までは本業に戻るとしましょうか。」
の姿が見えなくなったあと、整えられた庭や行き交う生徒らを眺めながら、骸は呟いた。
調査だけならまだしも令嬢の執事という肩書きがあっては休む間もない任務ではあったが、骸にとっては十分に楽しめる玩具のひとつに違いなかった。
「だから、本当なんだって。私に対しては暴言の連続なのよ?」
「そう感じてるだけじゃないのかな。悪口なんて彼が言えそうにないもの。」
「騙されてるのよ、パオラは!」
2限目、古代ローマ史の講義を終えた2人は、食堂にいた。
食堂の端、グランドピアノが置かれている隣の席で、今日も昼食をとっている。
朝から今まで、骸の話題で持ちきりだった。
いつの間にか他の友人らも参加し、若き女学生は皆、"の新しい執事"について興味津々だ。
「そんなにハンサムなの?」
「それはもう!みんなにも見せたかったわ!オッドアイというのかしら?両の目の色が違って不思議な雰囲気を纏っているけど、笑顔がとっても爽やか。物腰も柔らかくて、正に紳士ね。」
うっとりとした目で解説をするパオラに、を除く友人らは夢中で聞き入っている。
一方は、馬鹿馬鹿しいとでも言いたげな表情でカプチーノを飲む。
何度も骸の本性を説いたにも関わらず、誰一人としての言葉に賛同してくれないのだ。
「は厳しすぎるわ。執事さんをもっと大切にしなきゃ。」
「きっとを思って仕方なく言っているのよ。受け止めてあげたら?」
「もしかして、妬いてるの?大事な執事さんにパオラが夢中で。」
友人らのアドバイスともとれる言葉たちを聞き流していたが、最後の一つだけはそうもいかない。
「誰が妬くもんですか!あんな嫌味な男、今すぐにでも差し上げるのに!」
勢いよく立ち上がり、テーブルを両手で叩きながら怒りに任せて発した声は、食堂中に響いた。
好奇の目がに向けられ、ようやく落ち着きを取り戻す。
その様子を見た友人達は、「やっぱり妬いているのね。」と声を揃えた。
「ごめんなさい、そんなつもりじゃないの。素敵だなって、そう思っただけよ?気を悪くしないで、ね?」
申し訳なさそうにを宥めるパオラに罪悪感を抱き、それ以上は何も言わずに、ただ頷いた。
本心としては、まったく妬いてなどいないし、そもそも妬く理由もないわけで、それを熱弁したくもあったが、友人の心遣いを汲み取り、それ以上声を荒げるのは避けたのだ。
その後、3限4限と続いた講義の間中、骸に対する苛立ちと戦いながらもどうにか無事に全てを終えて帰宅しようとしたところ、昼食時のメンバーがへ駆け寄ってくる。
理由は聞くまでもない、骸を見るために集まったのだろう。
ここで断れば自分の立場を悪くするだけだと悟ったは、諦めたように承諾をする。
友人らを引き連れ校舎を出て門へ向かえば、既に車を止めて骸が立っていた。
「彼よ!ねえ、ハンサムでしょう?」
パオラが指差すと、黄色い声が次々に上がる。
皆パオラと同様、口々に「ハンサムだ」と感激する中、もちろんは黙っている。
−−−顔だけみれば、ね。だけど口を開いたらとんでもない性悪なんだから。
その犯人を指差し叫んでやりたいが、ここは学校だし、何より誰も信じてくれない。
友人達を説得することを諦めたが何も言わず車へと進めば、軽くお辞儀をした骸が後部座席のドアを開く。
そんな、どうってことのない振る舞いにも、周りはいちいち騒ぐのだ。
「それでは、また明日。ごきげんよう!」
語尾にやや力を込めながらそう告げ、ドアが閉じるのを待った。
外からは相変わらず黄色い声が聞こえてくるが、それに反しての機嫌は悪くなるばかり。
発車してしばらくすれば友人らの声も消えてしまったが怒りは治まるわけもない。
「あなたって、まるで役者ね。あちらとこちらでは、別人ですもの。」
「仰る意味が分かりかねますね。言いたいことがあるなら、はっきりとどうぞ。」
「その口ぶりに腹が立っていると言いたいの。どうしてあなたが私の執事なのかしら。」
「おやおや、貴女の認識は世間とはかけ離れていますよ。現にご学友は僕に興味津々のようでしたが?」
フロントミラーを割ってやりたい衝動に駆られたが拳を握り締めることで湧き上がる怒りを抑えた。
そして移り行く景色に視線を向けながら、今夜は骸を出し抜き、家を出てやろうとは決意を固める。
いつもの作戦は頭の中で破り捨て、新しい手段を探してみるが、どれも使い古された策ばかりだ。
溜め息をつきガラスに落書きをするをミラー越しに一瞥する骸の顔には、やはり笑みが浮かんでいた。
車中から頭を悩ませていただったが夜になっても名案は浮かばず、その日も翌日も、その翌日も抜け出すことができずにいた。
が何か行動を起こそうとすればまるで監視カメラで見ていたかのようなタイミングでドアがノックされ、骸が顔を出すからだ。
あまりのタイミングに何度溜め息をついたことか自身数えるのも馬鹿馬鹿しいとすら思うし、悔しいがお手上げ状態だった。
「眠れないのでしたら、本でも読んで差し上げましょうか?」
「いいえ、結構。でも、暇つぶしに六道さんのことを教えて。考えてみたら、私あなたのこと何も知らないのよ。」
そうきたかと骸は一瞬思案するも、すぐに頭を切り替える。
潜入に際して骸の経歴は完璧に作りこまれており、更には信憑性に欠けぬよう事実を織り交ぜているほどの徹底ぶりだ。
彼女がどこまで知っているかは定かでないが、作られた経歴を述べても面白味がない。
不思議とに嘘を並べる気を失くした骸は伝えることのできる過去を探し始めた。
「僕について知りたがるなど、貴女も物好きですね。何から話しましょうか?日本のことはどうですか?」
「うんうん、ぜひ聞かせて。」
「10代半ばでイタリアから日本へ渡りました。平和で、趣があり、そして季節により色が変わり、子どもながらに美しい国だと感銘を受けましたね。さんは春の日本を訪れたことは?夜桜といいましてね、月明かりに映る桜が実に幻想的です。」
「ママから聞いたことがある。私は見たことないけれど。」
「幼少時代は日本でお過ごしでしたね?」
「生まれは日本よ。だけど向こうでの記憶はあまりないの。物心つく頃にはここにいたから。」
それから二人は日本について語り合った。食事について、言葉について、文化について、人について。
日本での記憶が少なくも興味は深いに、骸は自分の見てきたその国のあらゆる面を言い伝える。
こんなにも穏やかな会話の応酬は、骸がこの屋敷を訪れて以来初めてだった。
当初は、の過去に触れることで父についての情報を得ようと考えていた骸であったが、あまりに目を輝かせて聞き入るを前にして、いつの間にか目的を忘れていた。
「さて、おとぎ話はここまでにして、よい子はそろそろ寝ましょうか。」
の相槌がどことなくまどろみを含んできたことを感じた骸は頃合いかと会話を切る。
子ども扱いされたことに少々腹を立てたであったが、不思議と不快感はなかった。
「おやすみなさい。」
「おやすみなさいませ、良い夢を。」
の瞼が完全に閉じたのを確認して骸は部屋をあとにする。
先ほどの会話を思い出し、自分としたことがお喋りが過ぎたと反省しながら、充足しているのも事実だった。